- 注目検索ワード

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は、情報セキュリティ・サイバーセキュリティの実装・運用支援をワンストップで提供する「コンサルティング事業」「ソリューション事業」と、企業のセキュリティ水準向上を内面から支援する「教育事業」を展開しています。
GSXでは「実践力・自衛力の向上」をキーワードに、経営層からエンジニア、一般従業員に至るまで、階層別の幅広い教育サービスを政府官公庁からエンドユーザー企業およびIT企業・SIerに提供しています。
特に「教育事業」では、近年のセキュリティ人材不足という社会問題とDXニーズの加速に伴うIT企業の課題に対し、全てのIT人材に向けた「プラス・セキュリティ人材の育成」と、各企業のビジネスモデル変革にも貢献できる「プラス・セキュリティを基軸にしたビジネス化」という相互成長モデルを確立し、全国の企業に積極的に提案しております。各人が実践できるセキュリティスキルを身につけることで、組織のDX推進と自衛力向上を実現します。

「セキュリティ教育講座」SIer・IT企業のエンジニアに求められるセキュリティ技術
Download »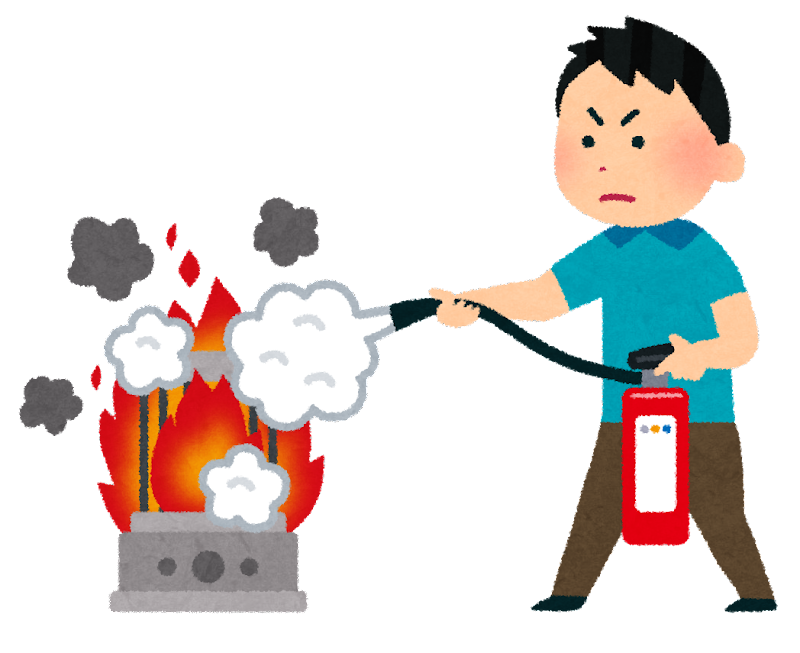
「インシデント対応訓練サービス(2023/2)」サイバー被害を最小で食い止めるインシデント対応訓練のステップとは?
Download »
「GSX標的型メール訓練サービス(2022/12)」GSXが2022年度顧客向けに実施した標的型メール訓練の傾向全公開!
Download »
東芝ITサービス 三人の“平熱”サイバーセキュリティプロフェッショナル ~ EC-Council 活用事例
Read more »
「セキュリティがわからなければお客様に選んでもらえなくなる」リスキリングによる技術者の“プラスセキュリティ人材化”で DX 時代に躍進する SIer と SES
Read more »
怒りと無力感…新生 GSX 社長 青柳史郎の原点とは
Read more »
ユーザー企業 “セキュリティ独立宣言” の旗印、グローバルセキュリティエキスパート株式会社
Read more »
「人材不足と丸投げ体質が課題」、GSX西日本支社がセキュリティエンジニア教育に本格的に取り組む理由
Read more »
Vex と SecuriST、ふたつの脆弱性診断の資格を軸に「日本のセキュリティを取り戻す」
Read more »![で、どうやったら SecuriST に合格できるか教えてもらえませんか上野さん ~ 非エンジニア文系ライター受験記 [後編]](/feature/gigaindex/3367/images/interview6.png)
で、どうやったら SecuriST に合格できるか教えてもらえませんか上野さん ~ 非エンジニア文系ライター受験記 [後編]
Read more »![非エンジニアの文系ライターが挑んだSecuriST認定ネットワーク脆弱性診断士受験記 [前編] もしもう一度ゼロからやり直せるなら](/feature/gigaindex/3367/images/interview5.jpg)
非エンジニアの文系ライターが挑んだSecuriST認定ネットワーク脆弱性診断士受験記 [前編] もしもう一度ゼロからやり直せるなら
Read more »
セキュアイノベーション、エンジニア育成にGSX提供「セキュリスト(SecuriST)認定脆弱性診断士 公式トレーニング」活用
Read more »
GSX、EC-Council公式トレーニングコースCEHv11リリース、杉浦隆幸氏と新井悠氏がゲストのイベントも開催
Read more »
GSXとKELグループ3社、セキュリスト活用した「セキュリティエンジニア育成プロジェクト」開始
Read more »
GSXの認定資格制度「セキュリスト」をNTTデータ先端技術が導入、受講と資格取得を推進
Read more »
情報システムグループの谷口 暢(たにぐち とおる)は、上司である村山 誠治(むらやま せいじ)からタイムカードが押せないと言われたとき、最初は PC の不具合を疑った。だがどうやらそうではない。解決するためサーバルームに赴いて当該サーバを確認すると、見たことがないファイルをふたつ発見した。ファイルの片方は「Lockbit2.0」と読めた。株式会社NITTAN のランサムウェア攻撃との戦いはこのようにして始まった。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は9月12日、同社が参画する日本サイバーセキュリティファンド1号投資事業有限責任組合(NCSF)が、第一号投資先として「セキュリオ」を提供するLRM株式会社への投資を決定したと発表した。

株式会社エーアイセキュリティラボは10月8日に、グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)と共催でセミナー「サイバーレジリエンス実現への最短ルート~事業を止めない「守り」と「回復」の秘訣~」を開催すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は7月29日、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)の営業・エンジニア4,000名に「SecuriST」や「EC Council」といった資格認定講座を提供することで、セキュリティ人材育成を支援すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は5月14日、2024年4月に立ち上げた日本サイバーセキュリティファンドに新たに9社が加わり全25社に拡大したと発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は5月21日、GSXが提供するセキュリティ人材育成講座の販売代理店契約を株式会社NTTデータと締結し、NTTデータを通じ、株式会社NTTデータグループおよびその顧客に提供すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は2月25日、丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社と連携し、「Box設定診断サービス」の提供を開始すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は1月24日、SecuriSTの新講座として「CISO講座」の提供を開始すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は9月24日、イスラエルのULTRA RED, Ltd.が提供する 「ULTRA RED」の取り扱いと運用サービスの提供を開始すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は7月26日、兼松株式会社にサイバーセキュリティ教育講座を提供しセキュリティ人材の育成を支援すると発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は7月29日、「日本サイバーセキュリティファンド1号投資事業有限責任組合」にLimited Partner(出資企業)として参画する16社を発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)と丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社(MIH)は6月27日、MIHがGSXの株式を取得する事で資本業務提携を締結したと発表した。

ファンド設立の狙いと目標は何か。本ファンドを最初に構想・発案した青柳氏に話を聞いた。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は3月29日、同社コンサルティング本部 教育事業部の小林浩史氏の「EC-COUNCIL Instructor Circle of Excellence」受賞を発表した。

兼松株式会社、兼松エレクトロニクス株式会社(KEL)、グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は3月25日、ウエルインベストメント株式会社を無限責任組合員とした「日本サイバーセキュリティファンド1号投資事業有限責任組合」の設立を発表した。

CyberSTARが4月1日から始動したと発表した。同社はGSXの100%子会社であり、セキュリティ人材特化型SES(システムエンジニアリングサービス)事業の専門会社として独立した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は3月1日、「IT-BCP文書雛形パッケージ(QAサポート付)」及びアドバイザリーサービスのリリースを発表した。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)は11月10日、株式会社ブロードバンドセキュリティ(BBSec)の株式を追加取得すると発表した。

その瞬間、返す言葉が見当たらず、何も言うことができない沈黙の時間が流れた。

株式会社LogStareは9月7日、グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)と協業し、ログ分析プラットフォーム「LogStare M365」とセキュリティ診断をワンストップで提供すると発表した。

記者はこれまで少なくない回数「顧客の笑顔が仕事の目標」といった趣旨の発言を何度も聞いてきた。だが、不思議に心動かされる言葉として取材時に耳に聞こえたし、何かハートが伝わった実感が今も消えずに胸に残る。